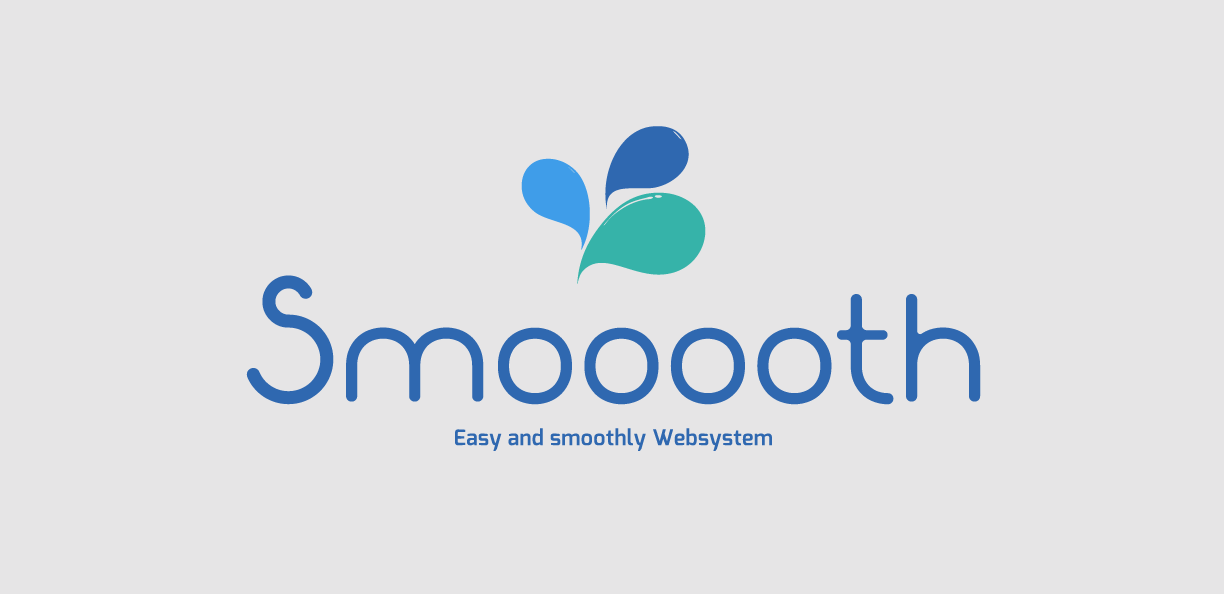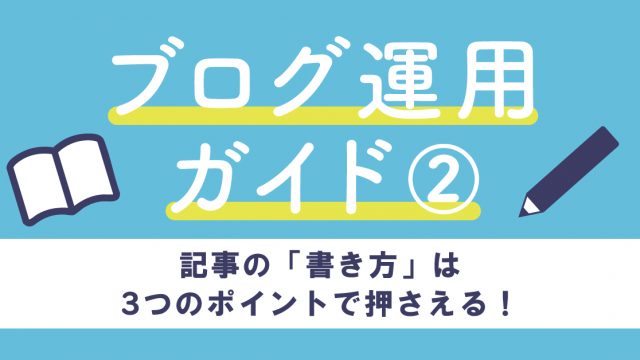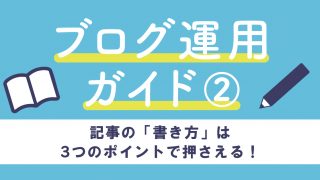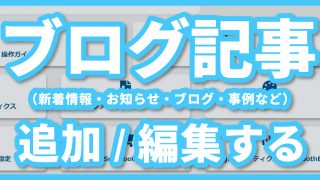
はじめに:「内容のある」ブログが評価される
上記の方法でホームページに記載していくブログ。
サイトの更新頻度を上げることで
・よりサイトが最新の状態であることをアピールする
・サイトの内容量を高めることで、Googleなどの検索エンジンへの働きかけを強化する
等、メリットはたくさんあるように思えます。
ただ…やみくもにブログを更新しようとしていませんか?
時代は終わりました!
昔は「ブログにキーワードをたくさん入れれば検索に強い」と言われていました。
でも今の検索エンジンの発達で、単に言葉を並べただけの記事よりも、「読む人の疑問にしっかり答えている記事」の高評価は顕著になりつつあります。
「とりあえず単語をいっぱい書けば点が稼げた」時代から
「ちゃんと先生の質問に的確に答えてる子が点数をもらえる」時代になりつつあります。
この記事では、その第一歩として「ブログを書く目的」を決めましょう。
「まず目的」⇒「頻度」⇒「内容」です!
自社やサイトにあった更新ができるかどうかをまず見直しましょう!
ターゲット・目的と理想の頻度
① 集客・SEO目的
サイトを作る目的の第一が
「アクセスを増やしたい」「検索で見つけてもらいたい」という場合はここです。
更新頻度のポイントは「継続的」
Googleなどの検索エンジンはサイトの更新の指標として「継続的に更新されているか」を挙げている傾向があります。
理想は「週2~3回」の投稿。最低でも「週1回」は確保をしたいところです。
特に新規サイトの場合は
「見つけてもらうためのコンテンツ量」を早く確保したいところです。
ユーザーから見て「充実している」と思ってもらえるか
検索エンジンからは「インデックス(検索結果に登録)される」か
を念頭に置いて、記事を増やしていきましょう。
この目的でブログを書く上でやってはいけないことは
「最初だけ大量に書いてすぐに止まること」。
立ち上げ時に勢いよく記事を出しても、その後に更新が途絶えると検索エンジンから「活動していないサイト」と見なされ、インデックスや評価が進みにくくなります。
また、検索を意識しすぎてキーワードを詰め込みすぎるのも逆効果。
ユーザーが読みにくく離脱してしまい、結果的に評価が下がります。
「継続して良質な記事を積み上げる」ことに尽きます。
② ブランディング・信頼感アップ目的
「会社の姿勢を示したい」
「専門性を伝えて、商談前などに見られた時にも信頼感を得られるようにしておきたい」
といった目的の場合は、ここになります。
更新頻度のポイントは「定期的」
サイトが「より強化された名刺」と考えると、
ブログは「定期的に顔を出す名刺」のような役割を果たします。
情報が途切れずに発信されていると、
閲覧者は「この会社はきちんと活動している」「安心できる」と感じます。
理想は「週1回~月2回」程度は確保したいところです。
この目的でブログを書く上でやってはいけないことは
「最終更新から期間が経ちすぎている事」。
どれだけサイト開設後に記事数を伸ばしても、最終更新から数か月空いているブログ一覧ページはユーザーに「止まっている」(=「この会社、もう活動してないのかな?」)といった、マイナスイメージを与えることになります。
記事の用意の仕方や、投稿時期にも気を付けた運用が重要です。
③ ファン向け・社内広報向けの目的
「既存のお客様に親しんでもらいたい」「社内の雰囲気を知ってもらいたい」
これがブログの目的であればここ。
更新頻度よりも「中身」を重視すべし!
ブログで重視すべき点が「今」である以上、社員インタビューや裏側のストーリーなど、1本の記事が“読んで価値があるかどうか”が重要です。
また、この場合だとユーザーの多くは「ある程度、閲覧に時間をかけてくれる」可能性があります。しっかり内容をくみ上げて、良質な記事を「2か月に1回」程度でもアップできれば効果的です。
この目的でブログを書く上でやってはいけないことは
「内容が薄いまま更新を優先すること」。
「とりあえず月に何本か出せばいいだろう」と考えてしまうと、かえって逆効果です。
ファンや社内の人たちは「その会社らしさ」や「他にはないストーリー」を期待して記事を読みに来ます。
その期待を裏切ってしまうと、更新が多くても読まれなくなり、せっかくのファンが離れてしまいます。
更新頻度は少なくても構わないので、1本1本を丁寧に仕上げることがポイントです。
さいごに:「目的⇒頻度⇒内容」の鉄則
ブログを書くときに
「とにかく更新しましょう」とだけ考えると、
途中で息切れしてしまいます。
結果として“やめてしまったブログ”が最大のマイナス要因になり得る可能性もあります。
でも「なぜ書くのか?」という目的を明確にすれば、必要な更新頻度も自然と見えてきます。自社のブログの役割を整理し、どの目的で運用していくのかを決めることから始めましょう。